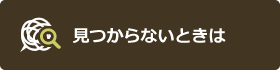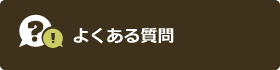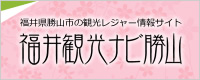本文
国民健康保険税について
国民健康保険税とは
国民健康保険税は、加入している皆さんが、保険に要する費用の一部を負担しあう税です。保険税は、みなさんが病気やけがをしたときの医療費の支払いに充てられることから大切な財源となりますので、必ず納期内に納付しましょう。
納税義務者
国民健康保険税の納税義務は世帯主にあります。このため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、納税通知書は世帯主宛てに送付されます。
たとえば、世帯主が勤務先の健康保険に入っていたり、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に入っていたりして、国民健康保険に加入していなくても、世帯に加入されている方がいれば、その世帯主が納税義務者となります。
保険税額の計算方法
国民健康保険税の総額を医療給付費分、後期高齢者支援金分、そして、介護保険納付金分の項目に割り振り、これらを組み合わせて世帯ごとの保険税額が決められます。 税率は下記のとおりです。
【医療給付費分】
・所得割額 課税標準額(※1) × 6.5%
・均等割額 被保険者1人あたり 26,500円
・平等割額 1世帯あたり 19,000円
・賦課限度額 660,000円
【後期高齢者支援金分】
・所得割額 課税標準額(※1) × 2.1%
・均等割額 被保険者1人あたり 8,500円
・平等割額 1世帯あたり 6,000円
・賦課限度額 260,000円
【介護納付金分】
介護分の対象者は、40歳から65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)となります。介護分は、満40歳になる月(1日が誕生日の方はその前月)から、満65歳になる前月分(1日が誕生日の方はその前々月)まで納めていただくことになります。
・所得割額 課税標準額(※1) × 1.8%
・均等割額 被保険者1人あたり 9,000円
・平等割額 1世帯あたり 4,000円
・賦課限度額 170,000円
※1)所得割の課税標準額
課税標準額 = 前年分の総所得金額等 - 430,000円
※注意事項
・年度途中で40歳になる方の介護分は、40歳到達月以降に上乗せされます。
・年度途中で65歳になる方の介護分は、あらかじめ65歳到達月以降の介護分を除いています。
・年度途中で75歳になる方については後期高齢者医療制度に移行するため、あらかじめ75歳到達月以降の保険税は計算に含めていません。
軽減について
世帯の所得が少ない場合は、世帯の所得水準に応じて均等割額と平等割額が軽減されます。世帯主とその世帯の被保険者の所得の合計が下記のときに該当します。
・7割軽減 : 43万円+10万円×(給与所得者等の人数−1)以下
・5割軽減 : 43万円 + (30.5万円 × 被保険者数と旧国保被保険者の合算数)+10万円×(給与所得者等の人数−1)以下
・2割軽減 : 43万円 + (56万円 × 被保険者数と旧国保被保険者の合算数)+10万円×(給与所得者等の人数−1)以下
・子どもの均等割軽減 : 未就学児に係る均等割保険料の5割を軽減
※上記の他に、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)創設に伴う軽減・緩和措置があります。
保険税の納税通知書
保険税は世帯ごとに算出し、納税義務者である世帯主の方に毎年7月中旬に納税通知書をお送りしています。また、税額に変更があったときや、7月以降に加入したときは届け出のあった月の翌月中旬にお送りします。
納付方法
納付については、最寄りの金融機関、コンビニエンスストア等で納付期限までに納めてください。スマートフォンなどのアプリを利用したキャッシュレス決済による納付も可能です。また、納め忘れや金融機関等へ足を運ぶ手間を無くすため、口座振替による納付方法もございます。
年金から引き落とし(特別徴収)
次の(1)から(3)にすべて該当する人は、国民健康保険税を10月に支給される年金から引き落とし(特別徴収)することになります。4月、6月、8月の年金支給時には前年度の保険税額で徴収を行います。保険税額が確定した後の10月、12月、2月に徴収を行い調整します。なお、65歳の誕生日を迎えた場合、その誕生月により、4月または10月から特別徴収が開始されます。
【年金引き落とし(特別徴収)の要件】
(1)世帯主が国民健康保険の被保険者である。
(2)世帯内の被保険者が全員65歳から74歳である。
(3)世帯主の年金が年額18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料の合計額が、年金額の2分の1以下である。
※なお、一定の要件を満たす場合、申請により、年金からの天引きを取りやめ、口座振替に切り替えることができますので、ご希望の方は市民課市民税係窓口までお越しください。
納付期限
1期 令和7年7月31日
2期 令和7年9月30日
3期 令和7年12月1日
4期 令和8年2月2日