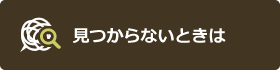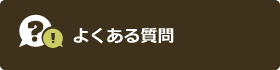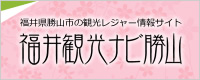本文
市県民税について
◆市県民税とは
個人の市県民税は原則として、その年の1月1日現在に住民登録のされている市町村で課税されます。また、住登外課税といって住民登録はなくても実際に住んでいる場合は居住地の市町村で課税されます。住民登録はなくても、事務所、事業所または家屋敷を有している方には均等割のみが課税されます。市県民税は「均等割」と前年の所得金額に応じて決まる「所得割」とがあり、その合計が市県民税となります。
◆市県民税が非課税の人
(ア)生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
(イ)障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
(ウ)前年の合計所得金額が38万円以下の人
(エ)控除対象配偶者または扶養親族等を有する場合は、前年の合計所得金額が(本人(1)+控除対象配偶者(1)+控除対象扶養親族数+16歳未満の扶養親族数)×28万円+26万8千円以下の人
合計所得金額とは<外部リンク>(国税庁ホームページより)
◆所得割が非課税の人
(ア)前年における総所得金額等が45万円以下の人
(イ)控除対象配偶者または扶養親族等有する場合は、前年における総所得金額等が(本人(1)+控除対象配偶者(1)+控除対象扶養親族数+16歳未満の扶養親族数)×35万円+42万円以下の人
(ウ)総所得金額等が所得控除額合計以下の人
総所得金額等とは<外部リンク>(国税庁ホームページより)
◆市県民税の納付の仕方
市県民税の納付は「給与からの特別徴収」と「年金からの特別徴収」、「普通徴収」のいずれかの方法で納付していただくことになります。
◇給与の特別徴収とは
お勤め先の会社より毎月支払われる給与から市県民税を支払っていただくものです。給与から差し引かれた市県民税は、会社の方で一括して従業員全員の市県民税分を市に納付します。
税額は5月中に会社を通じて通知されます。差し引かれる期間は6月から翌年5月までとなっています。
途中で会社を退職された場合は、残りの税額を最後の給与から一括で納付していただく方法(一括徴収)か個人で納付していただく普通徴収に切り替わります。
【例】年税額15,000円の方の場合、6月分1,800円・ 7月分から翌年5月分は毎月1,200円となります。
◇年金の特別徴収とは
平成21年10月よりスタートした制度です。これは、年金所得に該当する市民税分について、公的年金等から天引きを行うもので、高齢者の方の納税の手間を省き、市町村事務の効率化を図ることを目的に、全国の市町村で始められました。
これまでは、賦課期日(1月1日)後に他市町村に転出した場合や税額が変更された場合、年金からの天引きが中止され、天引きされなかった額については普通徴収(納付書で納めていただく方法)で納めていただいていましたが、平成28年度からは、一定要件の下で年金天引きが継続されます。
なお、年金が支給停止になった場合は、これまでどおり天引きが中止となり、天引きされなかった額については普通徴収で納めていただくことになります。
◇普通徴収とは
特別徴収以外の方は個人で市県民税を納付していただく普通徴収となります。
通常6月中旬に納税通知書が送付されますので、1年分を一括して納める全期前納か4期に分けて納めるかどちらかの方法で納付してください。
【例】年税額15,000円の方の場合、1期…6,000円、2期…3,000円、3期…3,000円、4期…3,000円 となります。
総所得金額・合計所得金額について
- 総所得金額・合計所得金額について (519.3 KB)