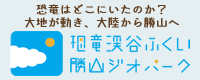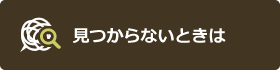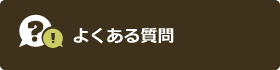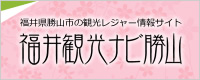本文
令和7度(1学期) 中学校でのESD
勝山市は、「児童生徒が主体の楽しくわかる学び」の実現に向け、授業改善やICT機器の効果的な活用等の取組を推進しています。
個別最適な学びと協働的な学びの在り方について研究を進めながら、楽しくわかる授業づくりに努めています。
その主体的な学びの一部として、ESD(持続可能な開発のための教育)を通した探究的な学習の支援を一層進め、予測困難な課題に立ち向かい、グローバル社会で活躍するために必要な自立する力、協働する力など多様な力の基礎を培っていきます。
また、勝山市の歴史・文化・産業・自然を題材にESDを展開し、ふるさとへの誇りと愛着心を育てていきます。
それらの目標を達成するために取り組んでいる各校の様子の一部を紹介します。

勝山南部中学校

1年生は地域の織物産業について理解を深めるため、蚕の飼育に取り組みました。
2年生は、防災教育に取り組み、地震が発生した街に住む中学生となり、校内図面と周辺地図を用いて、様々な状況の避難者を適切な場所に誘導する役割を疑似体験しました。
避難場所で使われる折り畳みベッドの体験を行い、避難生活の不自由さを体感することができました。
![]()
![]()
勝山中部中学校

全校生徒で「ふるさとクリーンアップ活動」を実施。校区内のごみ拾いや、本校の伝統である浄土寺川清掃活動に携わりました。校区の自然環境の実態を知り、「勝山のよさ」について考え、探究するきっかけとしました。
また、1学年では、収集したエコキャップを贈呈し、社会福祉協議会の方から、途上国の方々のワクチン接種にどのようにつながるのか、お話を伺いました。
![]()
![]()
勝山北部中学校

1,2年生で『勝山を美しく、元気に、有名に』というコンセプトのもと、北中まちづくりプロジェクトを行っています。
1年生は、「地域活性化と福祉貢献」をテーマに、勝山市の知名度やより良い環境づくりに関して街頭インタビューを行いました。2学期からは福祉施設や特別支援学校の訪問を行い、地域活性につながる活動を行う予定です。
2年生は、校区内の景観の美しさを伝えるためにポストカードを作成中です。その収益から、新たに花の苗を購入し、まちづくり会館や保育園に寄付する予定です。
![]()
![]()