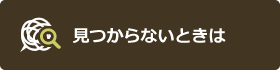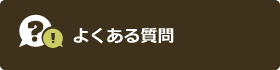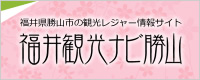本文
令和3年度(2学期) 小学校でのESD
2学期は新型コロナウィルス感染症が拡大している中スタートし、各学校行事や活動が数多く制限される中で、ESDに取り組んできました。
外部とのつながりは、対面だけでなくタブレットを用いてリモートをうまく活用することにより、何とか活動を展開することができました。
実際に足を運んで調べたり、専門の方に来ていただき話を聞いたりすることがどれだけ大切な学びであるかを実感しながら、今、できることを進めてきました。
11月に入ると新型コロナウィルス感染症の感染状況が落ち着いたことにより、体験したり、行事に参加したり、発表会でおうちの人に見てもらったりと、本来の活動ができるようになりました。

平泉寺小学校
白山平泉寺の未来の語り部活動!修学旅行で訪れた嶺南の今富小学校や一般観光客の方にもガイドを行い、日本遺産サミットでは取り組みを発信しました。PRグッズとしてエコバッグも製作しました。
また、今年も池ケ原湿原のヨシ刈りを行いました。そのヨシを使い、地域の方を講師として“ヒンメリ”づくりも行いました。
![]()
![]()
成器南小学校
5年生は、成器南校区の環境について学び、6月には特定外来生物のオオキンケイギク、9月には要注意外来生物のセイタカアワダチソウの駆除活動を行いました。セイタカアワダチソウはゆめおーれ勝山と連携してエコバッグの染め物体験に使用しました。
3年生は、自分たちの学校の前身である成器堂の旧講堂を見学に行き、学校の歴史について学びました。
![]()
![]()
成器西小学校

6年生は、ふるさとについて学習したことを、講師の方に教わってCMにまとめました。
3年生は、勝山市にある江戸時代に建てられた住宅を見学に行き、家のつくりや昔の人が使っていた囲炉裏や馬小屋など、生活するための工夫を学びました。
![]()
村岡小学校
4年生は、笑顔あふれる町にするために、赤ちゃん体験と幼児との交流に続き、シニア体験を行い、お年寄りの気持ちになって考える学習を行いました。
5年生は、春に田植えを行い、成長を観察し続けてきた稲を刈って、収穫を体験しました。身近にある大切な自然の恵をいただきながら、守り続けていかなければならないことを学びました。
![]()
![]()
三室小学校
1、2年生はまちづくりの一環として、応援ネットワークの方と一緒に公民館の駐車場で自分の考えたタイルを貼り付けました。ふるさとへの愛着が高まったと思います。
3、4年生は、シニア体験や車いす体験を通して興味を持ったことを、さらに調べるために課題を整理し、自分たちができることを考えました。5、6年生は、三室川で水生生物の調査を継続しました。
![]()
![]()
野向小学校


毎年、上の学年が下の学年に教えたり、地域の方に教わったりしながら、学習発表会で披露してきた雅楽は、今年度をもって活動を終えます。今年も立派な演奏を披露しました。
また、野向特産のエゴマや黒豆の栽培や収穫を行い、育てる大変さや食の大切さについて学びました。
![]()
![]()
荒土小学校

4年生は荒土町にある復元炭焼き窯で、原木入れや炭出しなどの炭焼き体験をしました。炭にする原木を苗木から育て、植樹する体験もしました。
5年生は、地域の農家の方の田んぼで田植え、稲刈り体験をしました。また収穫した米でおにぎりを作ったり、刈り取った稲を使ってしめ縄を作ったりしました。
![]()
![]()
鹿谷小学校
3年生は、ふるさと学習の成果をもとに勝山旅行プランを作成し、勝山市の魅力をまとめる活動を行いました。市長さんにプレゼンした後、パンフレットや動画で市内外に情報発信しました。
5年生は、多くのホタルが見られる鹿谷川の水生生物と水質の調査をしました。川には、小さな魚や小エビ、カワニナなどたくさんの生物がいて、ややきれいな水質であることがわかりました。
![]()
![]()
北郷小学校

6年生は、勝山市の産業である織物の変遷を学習し、自分たちで育てた綿から糸を作って手織りの体験をしたり、ゆめおーれ勝山や白木興業に見学に行ったりしました。
5年生は、鳥獣被害をきっかけにして近くの山林に生息するクマや鹿などの動物や狩猟について学び、実際にジビエ料理を味わいました。
![]()
![]()