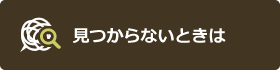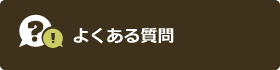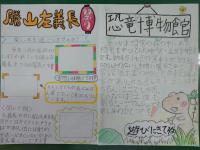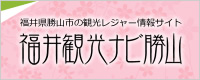本文
令和5年度(1学期) 小学校でのESD
令和5年度は、新型コロナウイルス感染症が5類に移行したことにより、多くの行事や交流が制限なく、コロナ禍前と同じように開催することができるようになりました。以前と同じ形に戻す活動があれば、縮小したまま実施する活動もあり、いろいろな意味で見直すきっかけになったと感じます。
勝山市としては、昨年度に引き続き「児童生徒が主体の楽しくわかる学び」の実現に向け、ICT機器の効果的な活用や授業改善等のさらなる取組を推進しています。特に、個別最適な学びと協働的な学びの在り方について研究を進めながら、楽しくわかる授業づくりに努めています。
その主体的な学びの一部として、ESD(持続可能な開発のための教育)を通した探究的な学習の支援を一層進め、予測困難な課題に立ち向かい、グローバル社会で活躍するために必要な自立する力、協働する力など多様な力の基礎を培っていきます。
また、勝山市の歴史・文化・産業・自然(ジオパークや恐竜を含む)を題材にESDを展開し、ふるさとへの誇りと愛着心を育てていきます。それらの目標を達成するために取り組んでいる各校の様子を紹介します。

平泉寺小学校
3、4年生は、5、6年生に教えてもらいながら、ヨシストローを作り、1、2年生には、ヨシストローに関する資料を作って発表し、環境保全活動について教えました。
5、6年生は、石文化でつながる「こまつの石文化」について学ぶため、「那谷寺」「小松市埋蔵文化財センター」「加賀国府ものがたり館」を見学し、白山平泉寺についてさらに理解を深めました。
![]()
![]()
成器南小学校
2年生は、自分が住んでいる地域のお店や施設などを訪問し、発見したひみつや工夫を「地域のすてき」として新聞やパンフレットで報告し合いました。
6年生は、グラフィックデザイナーの方からアドバイスをいただき、雪室そば粉のパッケージデザインや、勝山の魅力を詰め込んだ雪室そばメニューを考案しました。
![]()
![]()
成器西小学校
1年生は、地域の自分のお気に入りの場所(公園など)をクラスのみんなに紹介しました。そのあと、みんなで探検に出かけ、虫や植物を探したり、遊具で遊んだりしました。
6年生は、これまで訪れた市内の施設や調べた勝山の名産品を題材にして、修学旅行等で勝山市をPRするためのパンフレットを作成しました。
![]()
![]()
村岡小学校
3年生は、村岡の自慢である、村岡山について商工文化課の町さんからお話を聞き、さらに詳しく調べ、壁新聞にまとめました。
6年生は、「未来へつなげよう」をテーマに、村岡小学校の伝統であるミチノクフクジュソウの保全活動に今年度も取り組み、この活動を通して身の回りの環境に大切さについて学んでいます。
![]()
![]()
三室小学校
全校で三室の畑にて、安全でおいしい野菜を栽培しました。5、6年生は、野菜づくりを通して様々な知恵を学びました。
1、2年生は、生活科で地域の方と三室山に登り、色々な虫や植物を発見し、豊かな自然環境を他の地域に発信するための方法を考えました。恒例行事の原始運動会では、工夫を凝らした三室ならではの競技をみんなで楽しむことができました。
![]()
![]()
野向小学校

3、4年生は、地域の高齢者の方と一緒にできる遊びを考えて、ゲームを楽しんだり、手話ダンスやリコーダー演奏を披露したりして交流しました。
5、6年生は、野向町の特産であり、自分たちも毎年栽培に携わっているえごまの魅力を伝えるため、地域の方のインタビューを盛り込んだCMをつくりました。
![]()
![]()
荒土小学校
4年生は、広葉樹の苗木を育て、その苗木の植樹や炭焼きの窯入れから窯出しまでの体験を通し、今年も環境や地域の人とのつながりについて学びました。
5年生は、地域の農家の方の協力を得て、田植えを体験しました。その後も生育状況を観察したり、他の品種を比較したりして、コシヒカリの良さを発見しました。
![]()
![]()
鹿谷小学校

5年生は、地域や鹿谷まちづくり会館の方を招いて鹿谷町特産の恐竜ひょうたんについて学び、栽培に取り組みました。また、他学年に呼びかけ、希望する児童へひょうたん栽培の指導を行いました。
6年生は、勝山市や鹿谷をPRするために、発信する内容を絞り込み、自分たちが知らないことについては地域の方に尋ね、情報収集を行いました。
![]()
![]()
北郷小学校


3年生は、家族への聞き取りや地区の川の現地調査、タブレットを使った検索、まちづくり会館の方に話を聞くなどして、地域の魅力である川やアユについて調べ学習を行い、調べたことをクラスで共有しました。
6年生は、「ゆめおーれ勝山」の協力のもと、地域にある施設「旧木下家住宅」で織物等の勝山の歴史について学びました。また、今年100周年を迎える小舟渡橋の歴史についても学びました。
![]()
![]()