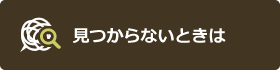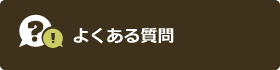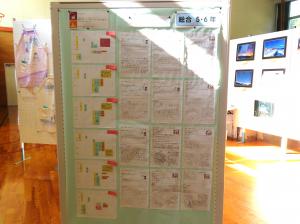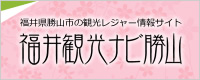本文
令和5年度(2学期) 小学校でのESD
2学期は、各学校が1学期に調べてきたことをもとにさらに深く、広く調べ、考えたことをまとめる時期です。
児童生徒が課題を設定し、調べたり考えたりしながら取り組んできたことを振り返る中で、さらに見えてくる課題を解決していこうとする場面が増えてきたように感じます。児童生徒が「もっと調べたい」という意欲は、学びを広げたり深めたりすることにつながります。
この活動がまさに「探究」と言え、これからの社会を生き抜くために必要な資質や能力を培うことができる時間であり、人間が直面している正解のない課題に取り組み続ける力になっていくと考えられます。
また、発信の手段として、ICTを使った学校間交流や各校での発表会、地域に出向いての発表、地域の魅力を題材にしたCMづくり等、多岐にわたって実践してきました。
児童生徒が再発見した勝山市の魅力について、たくさんの方と共有できれば、ありがたいです。
3学期は、今年度の取組について各学校・学年においてまとめを行い、次年度の方向性や目標等を明らかにし、準備を進めていく予定です。

平泉寺小学校

長年継続している、池ケ原湿原自然観察会を今年度も全校で2回行い、1、2年生は杉の子わくわく発表会にて、湿原に生息する生物について学んだことを報告しました。
5、6年生は、兵庫県丹波市との交流学習「竜学」にて、白山平泉寺を紹介する語り部活動を行い、丹波市の子どもたちに魅力を伝えました。
![]()
![]()
成器南小学校
3年生は地元で作られている勝山水菜について知るために、実際に栽培されている畑を訪れ間引き体験を行いました。学んだことを学習発表会で紹介しました。
5年生は校区にある町工場の工場長を招き、地元に根付く自動車部品製造についてお話を聞きました。
![]()
![]()
成器西小学校
3年生は地域の施設や企業を見学し、勝山市が誇る繊維産業について、その素晴らしさや私たちにできるSDGsについてまとめ、学習発表会で発信しました。
6年生は勝山市の良いところを調べ直し、勝山PRパンフレットを作成しました。そのパンフレットを修学旅行の時に、京都の観光客に配布しました。
![]()
![]()
村岡小学校
3年生は「村岡の自慢を発見」をテーマに、赤とんぼについて村岡女性の会の方からお話を聞いたり、赤とんぼ採集と採卵を行ったりして、赤とんぼの保全について学びました。
6年生は長年受け継がれているミチノクフクジュソウの保全活動について学んできたことをまとめ、緑の少年団として県の活動発表会にて発信しました。
![]()
![]()
三室小学校

2年生は1学期から作成してきた「三室虫カード」を使って、「まちのすてき」を学校外の人たちにも発信しました。まちづくり会館の職員からアドバイスをもらい、誰が読んでもわかりやすい新聞を作り、掲示しました。
5・6年生は三室自然帳を作り、学習発表会で展示しました。
![]()
![]()
野向小学校
5、6年生は、人口や産業の面から野向の未来について考え、将来の自分が、どのように野向と関わっていけるかを町民文化祭で発表したり、掲示物にまとめたりしました。
全学年で、豪雨で被害にあった野津又川の復興工事を見学して、被害の大きさや、復興のために働いている人たちがいることを知りました。
![]()
![]()
荒土小学校
4年生は、お年寄りはどのようなことに不自由を感じているのかを知るためにシニア体験をしたり、サロンを訪問して、お年寄りと交流したりしました。学んだことを生かして自分たちでサロンを企画しました。
6年生は、修学旅行で訪れた観光地や施設と勝山にある観光地と比べて、共通点や相違点を新聞にまとめました。
![]()
![]()
鹿谷小学校

4年生は、シニア体験を通してお年寄りへのサポートの仕方を学んだ上で、交流会を企画して、ニュースポーツを楽しみました。
4~6年生と勝山北部中学生とで、環境保全のためにセイタカアワダチソウの駆除を行いました。また、5年生では、いろいろな外来種について調べたことをパンフレットにまとめました。
![]()
![]()
北郷小学校

3年生は、内水面総合センターでアユやサクラマスなど川魚について学び、実際に九頭竜川にて漁協の方の協力を得て、人工授精を体験しました。
6年生は、地域にお住いの映像クリエイターを講師に招き、北郷の魅力を見つけたり、体験したりしたことを発信するためのCMづくりを行いました。
![]()
![]()