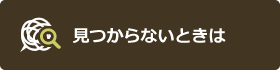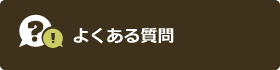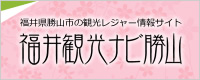本文
令和6年度(1学期) 小学校でのESD
勝山市は、「児童生徒が主体の楽しくわかる学び」の実現に向け、ICT機器の効果的な活用や授業改善等のさらなる取組を推進しています。
特に、個別最適な学びと協働的な学びの在り方について研究を進めながら、楽しくわかる授業づくりに努めています。その主体的な学びの一部として、ESD(持続可能な開発のための教育)を通した探究的な学習の支援を一層進め、予測困難な課題に立ち向かい、グローバル社会で活躍するために必要な自立する力、協働する力など多様な力の基礎を培っていきます。また、勝山市の歴史・文化・産業・自然を題材にESDを展開し、ふるさとへの誇りと愛着心を育てていきます。
それらの目標を達成するために取り組んでいる各校の様子の一部を紹介します。

平泉寺小学校
1・2年生は、自然保護センターの方をお招きして、池ケ原湿原の動植物について学びました。3・4年生は、ヨシストローづくりに挑戦し、今後、脱プラを発信していきます。
5・6年生は、笏谷石について学ぶため、福井市郷土歴史博物館や坂井市龍翔博物館などに見学に行きました。今後の平泉寺ガイドに生かしていく予定です。
![]()
![]()
成器南小学校
3年生は、市制70周年を迎える勝山市の魅力を発見し、発信するために、勝山まちづくり会館の方にガイドをしていただき、史跡めぐりをしました。
6年生は、勝山の魅力をCMとして発信するために、勝山市観光まちづくり会社の方に来ていただき、CMづくりのポイントを教えていただきました。2学期は、いよいよCMづくりに取り掛かります。
![]()
![]()
成器西小学校
5年生は「勝山の魅力発見プロジェクト」として、ゆめおーれ勝山やラコームを見学し、勝山の繊維産業について関心を高めることができました。
6年生は「勝山の魅力発信プロジェクト」として、これまでの総合的な学習の時間を振り返り、勝山PRパンフレットを作成しました。また、ラコームと連携し、廃材の布でオリジナルバッグづくりに取り組みました。
![]()
![]()
村岡小学校
3年生は、勝山の宝「恐竜」について調べるため、恐竜博物館に出かけたり、出前授業を受けたりし、ポスターにまとめました。
6年生は、「広げる!栄える!村岡の魅力」をテーマに、村岡小学校の伝統であるミチノクフクジュソウの保全活動に取り組み、ふるさとの魅力を守り受け継いでいます。
![]()
![]()
三室小学校
全校で縄文時代について学び、地域にある三室縄文遺跡への理解を深めました。学芸員の方から縄文時代の航海やおしゃれについて学びました。坂井市龍翔博物館や若狭縄文博物館、年稿博物館に見学に行きました。学んだことを取り入れて、児童が考案した競技や村まつりを楽しむ「縄文運動会」を開催しました。
![]()
![]()
野向小学校
3・4年生は、地域のコミュニティセンターで、お年寄りと交流会をしました。一緒にできる遊びを考え、クイズやゲームで楽しい時間を過ごしました。また、歌やリコーダー演奏を披露しました。
また、全校で三室の縄文遺跡資料室や大矢谷の白山神社に見学に行き、大昔の人々のくらしや自然について学びました。
![]()
![]()
荒土小学校
4年生は、どんぐりの苗木を育て、その苗木の植樹や炭焼きの窯入れから窯出しまでの体験を通して、環境保全や地域の人とのつながりについて学びました。
5年生は、地域の農家の方の協力を得て、田植えを体験しました。また、マイクロプラスチックの影響について学習し、荒土町のゴミ拾いを行いました。特定外来生物「オオキンケイギク」の駆除活動にも取り組みました。
![]()
![]()
鹿谷小学校

5年生は、地域や鹿谷まちづくり会館の方を招いて鹿谷町特産の恐竜ひょうたんについて学び、栽培に取り組みました。また、ホタルの生態や生息環境についても学びました。
6年生は、勝山市や鹿谷をPRするために、「自然・歴史・食べ物」のグループに分かれ、魅力を探りました。福井ふるさとCMを作る準備を進めています。
![]()
![]()
北郷小学校

5・6年生は、勝山市の織物の歴史について学びました。北郷町の織物の歴史についてゆめおーれ勝山の方からお話を聞き、綿を植えて育てました。
旧木下家を見学し、原始機を織る体験をしました。実際に蚕を育て、蚕がどのように繭になり、どうやって糸をとるのかについても学ぶことができました。
![]()
![]()