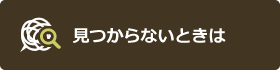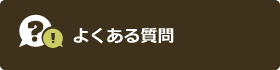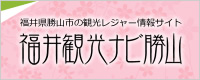本文
令和6年度(2学期) 中学校でのESD
勝山市は、「児童生徒が主体の楽しくわかる学び」の実現に向け、ICT機器の効果的な活用や授業改善等のさらなる取組を推進しています。
特に、個別最適な学びと協働的な学びの在り方について研究を進めながら、楽しくわかる授業づくりに努めています。その主体的な学びの一部として、ESD(持続可能な開発のための教育)を通した探究的な学習の支援を一層進め、予測困難な課題に立ち向かい、グローバル社会で活躍するために必要な自立する力、協働する力など多様な力の基礎を培っていきます。また、勝山市の歴史・文化・産業・自然を題材にESDを展開し、ふるさとへの誇りと愛着心を育てていきます。
それらの目標を達成するために取り組んでいる各校の様子の一部を紹介します。

勝山南部中学校

1年生は、生徒自ら地域の課題を見つけ、ふるさと勝山の良さを理解したり、知識を深めたりしました。
3年生は、実際に観光地に出かけ、地域の魅力を伝えるCMを作成しました。また、全校でボランティア活動に取組み、地域の清掃活動を行ったり、着なくなった服を集める「服の力プロジェクト」にも参加したりしました。
![]()
![]()
勝山中部中学校

1年生は、「15年後まで残していく」をテーマに、ミチノクフクジュソウ保全、エゴマの普及などに尽力されている方からお話を伺いました。
2年生は、かつやまっ子応援ネットワーク主催のイベントで、小学生を楽しませるために、7つのゲームを準備しました。どのゲームもとても盛り上がりました。
![]()
![]()
勝山北部中学校

1年生は、奥越特別支援学校を訪問し、自己紹介や出し物で交流しました。
3年生は、修学旅行先の東京とふるさと勝山を比較し、後輩を招いて発表会を行いました。学んだことや感じたことをポスターにまとめ発表することで、プレゼンテーション能力を高めることにつながりました。
![]()
![]()