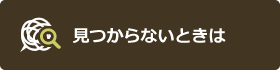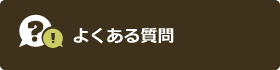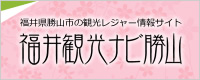本文
令和6年度(2学期) 小学校でのESD
勝山市は、「児童生徒が主体の楽しくわかる学び」の実現に向け、ICT機器の効果的な活用や授業改善等のさらなる取組を推進しています。
特に、個別最適な学びと協働的な学びの在り方について研究を進めながら、楽しくわかる授業づくりに努めています。その主体的な学びの一部として、ESD(持続可能な開発のための教育)を通した探究的な学習の支援を一層進め、予測困難な課題に立ち向かい、グローバル社会で活躍するために必要な自立する力、協働する力など多様な力の基礎を培っていきます。また、勝山市の歴史・文化・産業・自然を題材にESDを展開し、ふるさとへの誇りと愛着心を育てていきます。
それらの目標を達成するために取り組んでいる各校の様子の一部を紹介します。

平泉寺小学校

3・4年生は、平泉寺地区の方やヤマト運輸さんを招いて、ヨシストローづくりの交流会を行いました。また、11月には、全校で来年のヨシストローの材料にするヨシ刈りに行きました。
5・6年生は、修学旅行先の京都駅で平泉寺についてアンケートを行い、お礼にヨシストローを配布しました。
![]()
![]()
成器南小学校

3年生は、校区の企業、山一食品さんに来ていただき、大豆の魅力について語っていただきました。山一食品のきざみ油揚げや豆乳を生かしたメニュー作りに挑戦しました。5年生は、校区の休耕田を利用してどじょうの養殖をしている方から、始めたきっかけや勝山の未来についてお話を伺いました。6年生は、テーマごとに勝山の魅力をまとめ、CMを仕上げました。
![]()
![]()
成器西小学校

4年生は「人とのつながり」について考え、社協の方に協力していただき、マタニティ体験やお世話体験をしました。サロン交流の見学に行ったり、交流会を実践したりしました。シニア体験を通して、お年寄りへの理解を高めました。より多くの方との交流を目指して、勝山サンプラザで音楽会・交流会を開催しました。
![]()
![]()
村岡小学校

5年生は、「いちほまれちびっコンシェルジュ」として、田植え・稲刈りを体験し、いちほまれの魅力を全校や地域の方に紹介しました。
6年生は、これまで続けてきたミチノクフクジュソウ保全活動について、全国植樹祭で発表し、福井の魅力プレゼンテーション大会にも参加しました
![]()
![]()
三室小学校


講師を招いて、全校でミニ縄文土器を作りました。三室まつりでは、勾玉とミニ縄文土器を展示しました。
また、町民運動会では、自分たちが考えた縄文競技に取組み、保護者と一緒に楽しみました。縄文人について学んだことを各学年で学習発表会で劇にしたり、新聞にまとめたり、CMにまとめたりしました。
![]()
![]()
野向小学校

地域のコミュニティセンターと提携して、特産物のえごまの栽培を行いました。農家の方からやり方を教えてもらい、えごまの実落としや唐箕かけをしました。
また、百年ほど前から雅楽隊が活動してきた歴史を学び、地域の方をお招きして雅楽の演奏にも取組みました。
![]()
![]()
荒土小学校

5年生は、福井グリーンパワーの方を講師として、間伐材を原料としたカーボンニュートラルの実現に向け、バイオマス発電について学習しました。また、間伐材を使った割りばしづくりも体験し、袋などをデザインして、間伐割りばしを5000膳準備して、道の駅で販売を始めました。
![]()
![]()
鹿谷小学校

3・4年生は、ふるさとマップを作るために、志田神田遺跡について学びました。県埋蔵文化財調査センターから講師を招いて、縄文時代から古墳時代にかけての土器や遺跡を通して、鹿谷町の歴史について学びました。学んだことは、学習発表会で全校や地域の方に発表しました。
![]()
![]()
北郷小学校


5・6年生は、育てた綿を収穫し、糸にする体験をしました。種を取るのに時間がかかったり、すぐにちぎれてしまったりして難しさを感じました。戦時中に使われた落下傘を作ったり、ベンガラ染めに挑戦したり、織物や繊維産業についての学びを学習発表会で紹介しました。
![]()
![]()